夜景
しかし天気予報は見事に外れてましたネ。
12cmファンの威力は大きいです、取り付けるパネルの突起の関係でフィルタを内側に付けざる得ないのが気に入らないのですが。 本当は左のPen?W2.8GHz機に付けてやりたいのだけど...
栗坊さんのトラックバック企画から... しかし土曜日に梅雨入りした近畿、昨日から良い天気が続いてます、それも真夏日、どうやら明日も。 今年の梅雨も前半カラ梅雨、後半どこかで集中豪雨なんて事なのかな。
「雨の日に聴きたい曲」...ジーン・ケリーの「雨に唄えば」、太田裕美の「セプテンバー・レイン」(^_^;) ところで今夜からNHK-BS(アナログ)で3夜連続「ザッツ・エンターティント」Part1?3が放映されます「雨に唄えば」はたっふりと観られますね、私はPart3を見ていないだけに愉しみ愉しみ。
All Kinds of Weather / Ted Garland Trio (Prestige 7148)
から「Rain」かな。 小気味良いタッチとスィング感のガーランドのピアノ、この程度の爽やかな雨なら良いのだけど...
「おとし穴」「砂の女」「他人の顔」に続く安部公房原作?勅使河原宏監督の4作目、ユニークなのは製作プロダクションが勅使河原プロではなく勝新太郎の勝プロなのである、東宝配給による1968年の公開だがDVDに収録されている当時の予告編には大映の配給となっている、勝夫人の中村玉緒も勝の演じる主人公の別居中の妻の役として出演しているが、契約関係と倒産前の大映がどうなっていたのか私は詳しくない。 前3作とは異なりカラー作品で、私は30年程前に自主上映会の小さなスクリーンで見ているのだが、原作でも印象的な主人公が運転する軽自動車(スバル360)が坂道を登って行くシーンと失踪者の妻、すなわち主人公の探偵へ調査依頼をした「女」役の女優が印象(嫌いなタイプだと云う事で)に残っている位だった。 実はこの女優は’春川ますみ’だとずっと記憶していたのだったのだが、実は’市原悦子’だった事を知ったのは最近の事である。 なお勝の主演ともにユニークなのは渥美清の出演で妄想癖の男を良く演じている、他に長山藍子、信欣三、吉田日出子が出演している。
なぜ勝がこの原作をとりあげ自らが主演する事になったのか、一映画ファンに過ぎない私には良く判らないが、それでも不可解な印象を持ってしまう、勝の演技そのものは決して云々されるものではないと思うが、映画のタッチそのものは粟津潔によるタイトルデザインを除けば勅使河原作品と云うより1960年代の大映娯楽作品そのものであり、安部作品の持つ時代を越えた普遍性のようなものは汲み取れない、少なくとも安部公房ファンが観て納得できるものではないだろう。
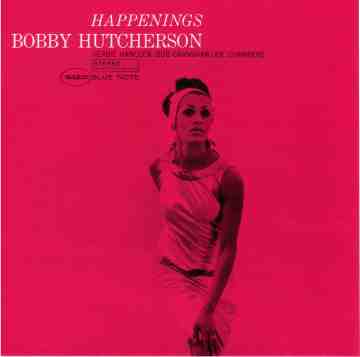
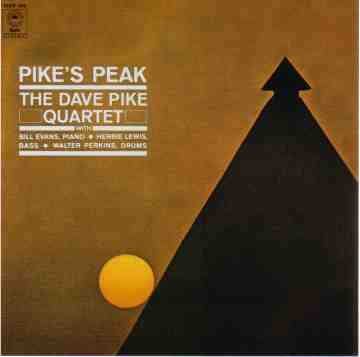
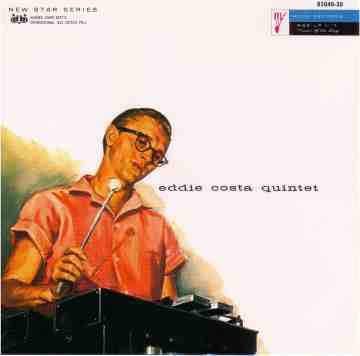
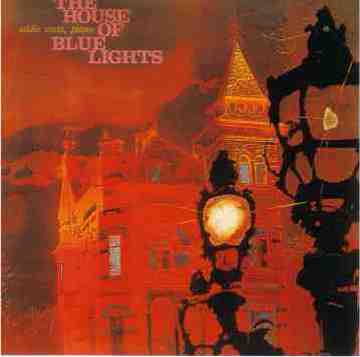

DOS/Vマシンを自作するにあたってなかなか良いケース選びと云うのも難しいものである。 指折り数えてみるとAT仕様ケースからだと十数台にもなる、最近お気に入りだったのはUAC製のUACC3303で3台をクライアント用として使用していたが、もう1台ほしいなぁと思っていると既にメーカー生産終了、あちこちのショップを探したり通販でも色々と当たってみたのだが、もう何処でも入手する事はできなかった、手に入らないと余計に欲しくなるものだが、もう手には入らないかと諦めてしまった頃、日本橋へ行った折、某ショップに1台展示されているではないか、先月はなかったのに(@_@) もちろん現品限りで電源付きのモデル、余計な電源が付いていて\12,980は高くもないが決して安くもない、しかしこれを逃したら二度とお目にかかる事はないだろうと買ってしまった。
と云う訳で晴れて?同じデザインのケースが写真の様に4台並ぶ事になってしまった(^_^;) で中身はと云うと余裕も計画もない事だから既存機を載せ換えている。
UACC-3303は5吋オープンベイ×6、3.5吋オープンベイ×2、3.5吋シャドウベイ×2と拡張性が高く、フロントカバーを閉じたままでも1台の5吋ベイはアクセス可能である、また後部に2つ、両サイドにそれぞれ8cmファンが取り付け可能、前面は5吋ベイ3台分と排他使用だが12cmファンを取り付ける事ができ、サーバー用としても充分使えるものである、マザー用バネルは独立していて後方への引き出しではなく右側面から斜めに取り付けるユニークな方法である、基本的にスクリューレス構造となっている。 ただ最近の傾向としてはいわゆる「「38゜シャーシ」に対応していないし、USB等のフロントアクセスも持っていないのだが、内部も丁寧な作りで色々と凝った仕掛けもある、この様に優れたケースが何故か廃版になってしまうのは些か残念である。 ネット上の個人HPでも自作マシンとして幾つか紹介されていて概ね評判は良い、確かに欠点や問題点も無くはない、サイドパネルがやや強度不足なのと、リアの8cmファンがファンにも拠るのかも知れないが寸法的に取り付けがキツい場合がある、フロントカバー付きのケースの宿命だがファンコントローラー等の前面に飛び出したベイアクセサリーは干渉する場合がある事は致し方ない。 同系シリーズで3305/3307がまだ残っている様だが、あのデザインはとても頂けない。 ショップのケース売り場に行くとド派手なデザインが目につくのだが、自作機マーケットではそうたったものの人気があるんでしょうかネェ...
前述の様に最上段の5吋ベイはカバーを開けずにアクセス可能だが、CD/DVD光学ドライブのベゼルやスイッチの位置や形状によっては使えない場合があるかも知れない。 電源スイッチ、リセットボタンと上段の3.54吋ベイは中央の小さなカバーを開いてアクセスが可能、なおフロントカバーは簡単に取り外す事が可能であるが、決して格好は良くないが(^_^) 中身の方は左から
Pentium?W 2.8GHz (Socket478 NorthWood FSB800MHz) / MSI PT880FISR / 512MB
Celeron 2.4GHZ (Socket478) / MSI PT880LSR / 512MB
Celeron 2.0GHZ (Socket478) / MSI PT880LSR / 512MB
Celeron 1.4GHZ (Socket370 Tualatin) / ASUS TUSL2-C / 384MB
いずれもハードディスクをシステム用とデータ用2台に分けて(概ね40G/80G)交換可能な様にリムーバブルケースに入れている。 ビデオカードは4台とも往年の名機?MatroxG450/32MBが頑張っている、ベンチマークの足を引っ張っている様な気がしないでもないが、切替器を使っている関係上異なるビデオカードだと微妙に同期周波数が変わってしまいモニター側をプリセットする必要がある。
UACC-3303は前述した様にUSB等のフロントアクセスを持っていないのでセリング製(ATN-TP-03C)の温度/回転数モニター(アラーム付き)がUSBとIEEE1394コネクタも持っているのでこれを取り付けている、どうやらこれも廃版らしくて4台目用が日本橋で見つけられなかったが通販で無事ゲットできた。
ところで上の写真で左端に黒い同型ケースが映っているが、実は4台目の3303を見つけた日、別の店で上位モデルの3301がジャンク扱いで\7,980(電源付き)で出ていた、元より付属電源は期待していないし、付属品や外見に問題は無いので思わずゲットしてしまった(^_^;) シャーシそのものは3303と同じで外板が高級なヘアライン仕上げでサイドパネルに透明の窓が付いている。
ただ今は中に何も入ってません、サイドに窓がついているついつい光り物のCPUファンが付いているP28マシンを入れ替えたいのですが... 現状ではハイスペックなマシンは必要としていないので幾つも余っているSocket370CPUを使って1台テスト用マシンをでっちあげても良いかなと。
4台目の3303の入手で引退したのは写真左、私が最初に買ったATXケースである、と云うよりAT機自作から暫く遠ざかっていたのでTWOTOPのキットを買ったものでVIPブランドが入っている、このケースは私の知る限りフロントパネル違いで他に3種のバリエーションがあって結構定番ケースとして人気があり、筐体もしっかりしていて4台が後から買ったケースを差し置いて今だ2台が現役(写真右)、1台が貰われて行って活躍中であった。 リムーバブルケースの使用が前提の私にとっては5吋オープンベイが3つと云うのは少ないです。
余談ですが’後から買った’とはバックパネルに汎用性がなかったもの2台(1台は譲渡、1台は部品取りして解体廃棄)、出来の悪い安物のアルミケース(ABIT BP6 370デュアルマザーにCeleron466MHz×2と500MHz×2を付けて’ともちゃ‘に譲渡)であった、結局は作りのしっかりした定番ケースが長生きするのですネ。
R氏の掲示板でも放熱の話題が出ていたが... スペック命のマニアックなマシンでもないし、ファンが必要なビデオカードを使っている訳でもないが(MatroxG450がいまも頑張ってます)、PrescotではないもののPentium?W 2.80CGHz (Socket478 NorthWood FSB800MHz)の発熱量は少なくはない、同系マザーにCeleron2.0GHzを載せたマシンに比べると5?7度は高い、リアに2個とサイドに1個の8吋ファンを回しているが、CPUやチップに電源の寿命を考えると涼しいに越した事はないので、サイドに1個、フロントに1個の吸気用のファンを増設してみた、リアの排気を大きくしても電源内部を経由する流れを妨げては逆効果なので多少なりとも吸気でケース内の与圧を上げてみる事にした。 なおこのケースUACC-3303は下部の5吋ベイを使用してしまうとフロントにファンは付けられなくなるのだが、空いている5吋ベイ2つ分にジャンク部品を使って写真の様にしてみた。 ちなみCPU温度で2?3度程は改善されている様だ(^_^)
ちなみにCPUファンはGIGABYTEのこんなのが付いていてフル回転させると効果絶大なのですがさすがにうるさい、ケースファンは電源のファン専用ラインで制御されているので、安いファンの割りにはうるさくないので余計に耳障りです。
PS:実は今一番耳障りなのは決して古くもないギガビット・スイッチ(IO-DATA)のファンなのです(>_<)
音楽にしろ映像作品にしろ、趣味的にも興味を持って長年関わると、個人的に思い入れのある作品やノスタルジックな感傷を持ってしまう作品がいくつかある。 「首」は1968年の東宝作品、ロードショーで見たのか、当時母親の入っていたタカシマヤ友の会の上映会で見たのか、さすがに記憶が曖昧なのだが、1968年当時では円谷特撮映画から「若大将」ものと多くがカラー化されていた時世に、鮮烈な白黒映像が今もなお印象に残っているものの、再び見る機会は40年近くもない。 決して大作ではないマイナーな作品だけに過去ビデオやDVD化された様子もなく、名画座や自主上映会などがないものか折々に気をつけていたのだが、ネットの時代でも「首」と云う短いタイトルは検索もしずらい、東宝作品ゆえフィルムが逸失してしまったなんて事はないだろうが、もしや二度とお目にかかる機会はないかも知れないとさえ思っていた。
監督は「八甲田山」や「日本沈没」を撮り1984年に53才で亡くなった森谷司郎、黒沢明監督のもとを離れ監督として独立して「赤頭巾ちゃん気をつけて」を撮るまでの初期の作品、原作は正木ひろし弁護士の実話小説でいわゆる「首なし事件」を題材にしている。 マイナーな作品と書いたが同年のキネマ旬報ベストテンでは「神々の深き欲望」「肉弾」「絞死刑」「黒部の太陽」と云った話題作大作に続いて第5位に入っている。 最近では「ツーカーS」のCMなんぞをやっているが、若かりし小林桂樹が主人公の弁護士役を演じていた。
実はその「首」がCSで放映される事を知ったが、CSを視聴する機器は持っていないので、あちこちあたるとS翁がケーブルテレビで見られると云う事で録画して貰う事になり(実はS翁はP女史に下請けに出したそうだが)、先日そのDVDを頂いた。
30数年ぶりの再開、確かに大作でもないし名作として名を連ねるものではないが、鮮烈な白黒映像、テンポの良いストーリー展開と充分に見応えのあるものだった、スタッフにはいわゆる黒沢組のメンバーが多く名を連ねているが、黒沢作品は初期作品からビデオ化DVD化され受け容れられるのに比べて、この作品が日の目を目見ないのが残念である。 スケールの大きな映像が求められ、悪く云えばコケ脅しばかりの最近の傾向ではこういった題材は映画どころかテレビドラマにもならないのかも知れないが、しっかりした作りの佳作秀作と云えるものである。